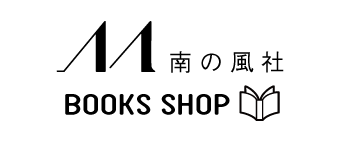高知県の出版社 南の風社の書籍を取り扱っています。
1冊からでも送料無料です。
Amazon Payでのお支払いもできます。
-

明治の和紙を変えた技術と人々 ~高知県・吉井源太の活動と交流~
¥1,980
著者:村上弥生 2020年11月1日発行 A5判(148mm ×210mm)、180ページ。 <目次> はじめに 第1章 吉井源太の履歴書 明治の時代と御用紙漉・吉井源太 大蔵省印刷局や内務省あての履歴書 幼い容堂を投げ飛ばす ユーモアある俳号と雅号 『日本製紙論』に見る御用紙漉の家系 第2章 開発された器具と色々な紙 簀桁を改良する 器具の改良・機械の活用 御用紙漉の薬袋紙 典具帖紙を世界へ 「コッピー紙」への高評価 透写に優れた紙 吸墨紙へ欧米から評価 軍用の防寒服用紙 第3章 種類を広げた原料と必需品 紙王とされた雁皮の紙 三椏の栽培奨励 楮確保の地道な取り組み 各種原料植物の適否 腐らないノリの探求 白さを高めるため米から白土へ 火と水に強い紙にする 官・民で勧業活動を 第4章 各地への伝習・巡回指導 教えを請う人々 明治二十年鳥取県巡回 ・雪深い坂を越えて ・各地区で連日の巡回指導 ・鳥取県巡回指導の終了 ・鳥取県巡回こぼれ話 明治二十九年愛媛県巡回の旅 新潟県へ派遣した仲間の訃報 全国に教師を派遣 修業来訪の人々 残る吉井源太の足跡 第5章 販路と組織についての活動 大阪の問屋専売から東京へ販路開拓 同業者組織設立への動き 紙業組合設立への貢献 海外を視野に 第6章 『日本製紙論』の出版 出版のきっかけと協力者 題辞と序文の依頼 ・題辞 ・序文 『日本製紙論』で説明される内容 幻となった続編 第7章 受賞と内国勧業博覧会出張 受賞した二つの褒賞 内国勧業博覧会の旅 ・明治二十三年東京上野 ・明治二十八年京都岡崎 第8章 色々な交流 中浜万次郎・中浜留 佐伯勝太郎 西本守太郎・松永雄樹 古稀の記念 現代への交流 ・吉井源太没後百十年記念企画展 ・五産地とのかかわり 第9章 コッピー紙について コッピー紙とは ジェームズ・ワットによるコピープレスの発明 ワットによるコピーペーパーの探求 コピープレスの日本への導入と使用方法 終章 吉井源太の活動の意味 おわりに
-

土佐ことば辞典 増補
¥1,760
SOLD OUT
2018年10月15日 増補版発行 A5判、212ページ <著者> 吉川 義一(よしかわぎいち) 高知大学名誉教授 農学博士 ーーー 〈土佐ことば〉は、土佐の歴史と風土に培われた独特の性格・感性をもつ土佐人が、日々の暮らしの中で、長い歴史を経て創り上げた、独特のすぐれた言語である。土佐の誇るべき文化である。表現の豊かさ、微妙さ、おもしろさを味わい、〈土佐ことば〉を通して、土佐人の気質や暮らしを、独特の優れた文化を理解していただければ幸いである。(「増補にあたって」より)
-

現代語訳 土佐物語 ー四国の勇士の戦国記ー
¥6,600
著者:中島 重勝 (抄訳) A5判、616ページ 2013年3月11日 発行 2017年1月17日 第2版 ーーー 宝永5(1708)年に長宗我部家臣の子孫・吉田孝世によって書かれた軍記物語「土佐物語」の現代語訳(抄訳)。 長宗我部元親の生涯を中心に、長宗我部氏の興起から滅亡に至るまでを描く。
-

土佐の郷士 龍馬たちの自由 対等 失業サムライの詩(うた)
¥1,540
2016年6月16日発行 A5判、144ページ 著者:福留 久司 <目次> はじめに 一、江戸時代の土佐では、すでに「近代」が誕生していた 二、土佐の郷士制度は山内藩の懐柔策から生まれた 三、土佐の「永小作権」は永久に所有できる権利だった 四、富を支配する魔法の言葉、「所有権」の誕生 五、「永代小作権」の自由・対等が民衆の中にとけ込んでいった 六、零細農民や庶民たちが主体となった市民革命を準備した 七、土佐が打ち立てた「分割所有権」は現民法272条に刻み込まれている 八、自由、対等、反骨の精神は今に引き継がれた おわりに [著者略歷〕 福留 久司(ふくどめひさし) 高知県香美市土佐山田町に生まれる 慶応義塾大学文学部卒業 高知県立大学大学院人間生活学研究科博士前期課程終了 高知県立大学大学院人間生活学研究科研究員 現在、学芸員
当ページ掲載は一部の書籍のみとなっておりますので、
その他お探しの本のご注文やお問い合わせにつきましては、
ご面倒ですがCONTACTフォームよりお願い致します。